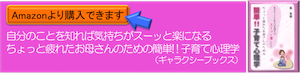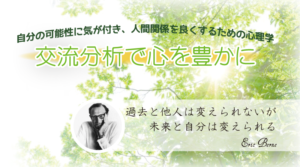ありがとうございます。
心理カウンセラーの島幸樹です。
先日カウンセリングセッションのときにもそんなお話をしたかもしれませんが、「障がい」とか「凸凹」とかを差別するなんてもってのほかなんだけど、かといって「その子の個性」だとかってリフレーミングする必要もないと思うのです。
「ちゃんとしなさい」って言われてちゃんとやれる人もいれば、それでは伝わらない人でため息をつかれている人もいる。
周りの人はサクサク解ける問題なのに、解けずにずっと怒られている人もいる。
それで他の人と比べて劣っているとか問題があるって言ってたら、ますますその人は人と関われなくなるかもしれません。
他の人はできるのに、どうしてこの人だけできないの?
または、どうしてわたしだけできないの?
と悩んでしまいます。
けど、そこに悩むのではなくて、同じ悩むとすれば「だったらどうしよう」を悩む方が良いと思うのです。
あいまいな表現だと何を言ってるのか伝わらないのであれば、具体的に行動レベルの言葉で説明するなり、やって見せるなりするということです。
「どうしてわからないの?」「なんで伝わらないの?」ではなくて「だったらどうしよう」。
他の子はサクサク解けるのにこの人だけ解けない。だったらどうしよう。口頭で説明したらどうだろう、絵に描いてみたらどうだろう、別の問題からアプローチしてみたらどうだろう。
「なんでこの人はダメなんだ」「なんでわたしはバカなんだ」ではなくて。ズブズブ落ち込んでいくのでもなくて。
目に障がいがある人に「どうしてここに書いてることがわからないの!?」って言わないですよね。視覚障がいも個性だよとは言わないですよね。
だったらどうしようって考えてみたら、いろいろと方法が思いつくんじゃないでしょうか。
いろいろやってみることができるんじゃないでしょうか。
いろいろ賛否のあること書いちゃうので不愉快な気持ちにさせてしまうかもしれませんが、障がいは障がいとして認識した方が、周りと比べて悲観したり自分を責めたりするより良いように思います。
イライラするのは嫌だし、怒りをぶつけてその人の自己肯定感を下げたりふさいでしまったりするよりも、だったらどうしようを試行錯誤する方に時間と心を使っていけたらなっていうのが私の考えです。
 ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。
ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。心理カウンセラー島幸樹の「心がスーッと楽になるメルマガ」
では読んでくださる皆さんの心に届き、読むだけで気持ちがスッキリする心理学、もっと素敵に生きられる心理学をメールマガジンにてお届けしています。
どうぞご登録ください(無料)。お待ちしています。
→心がスーッと楽になるメルマガの購読申し込みはこちら
心理カウンセラー・講師 島幸樹(しまさちき)
Heart Trust Communication 代表。
カウンセリングと心理学の学びをご提供し、自分らしい生き方を見つけるお手伝いをします。
専門は教育、発達心理学/カウンセリング心理学。学習塾の経営を経て、現在は講師・研修業と心理カウンセリングを行っています。
大阪生まれ。奈良在住。
さらに詳しい自己紹介はこちら。